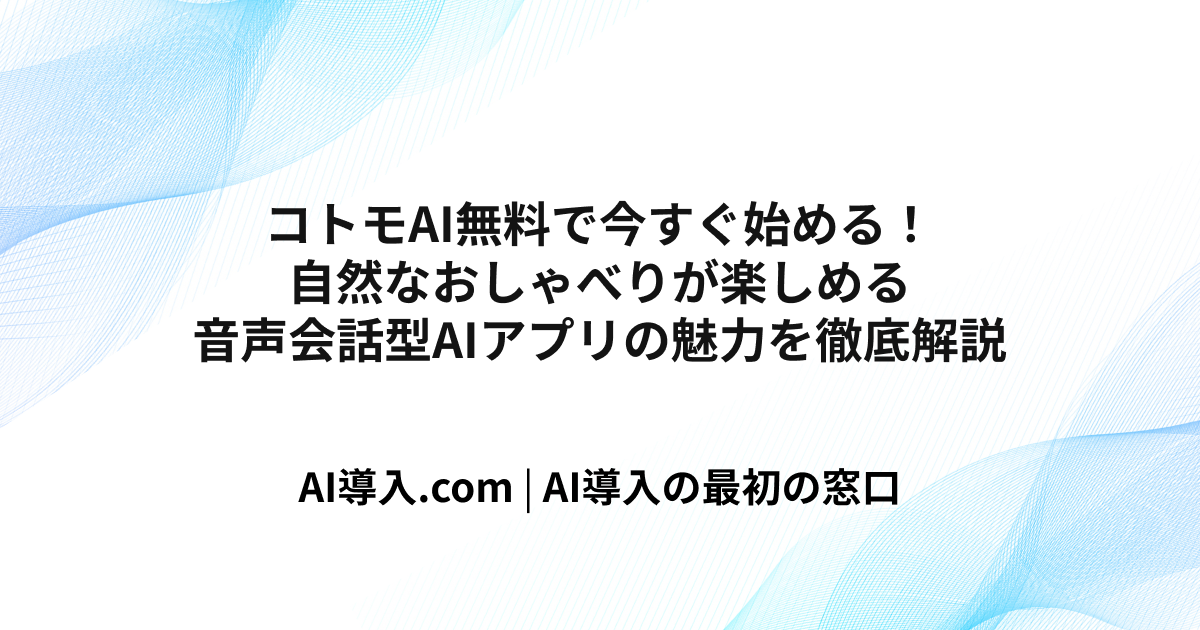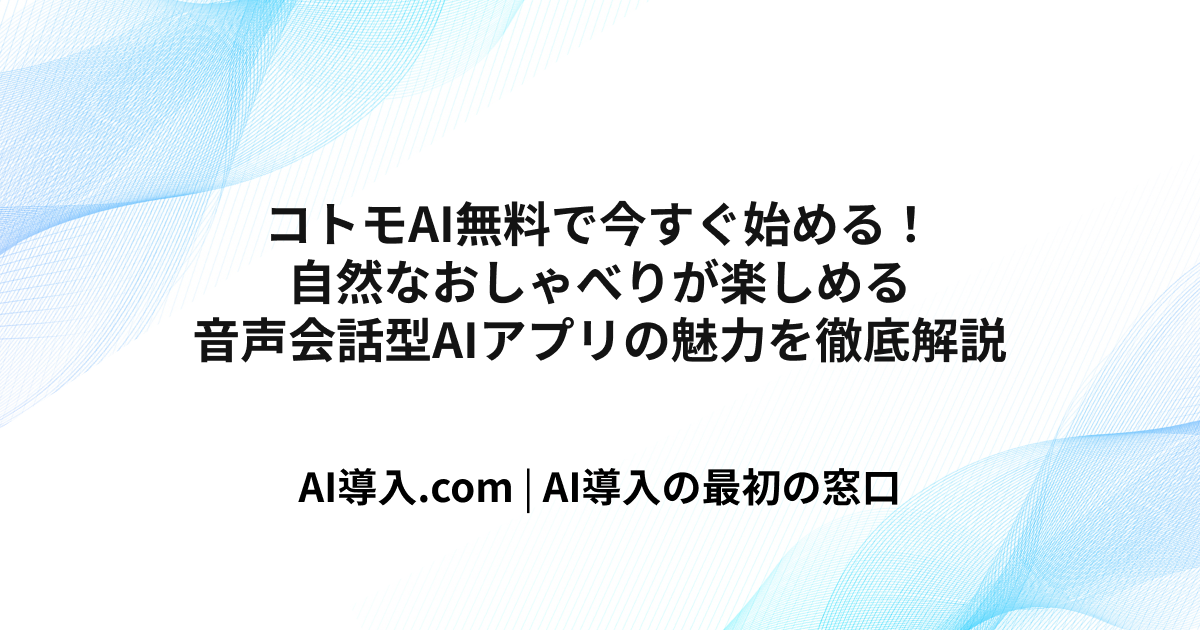コトモAI(Cotomo)の危険性とは?5大リスクと対策法を徹底解説
いま注目を集めている音声対話型AIアプリ「コトモAI(CotomoAI)」。2024年に登場して以来、自然な受け答えと高い共感性能が話題となり、多くのユーザーの「話し相手」として活躍しています。
しかし、その急成長と便利さの裏側には、プライバシーリスクやセキュリティ上の不安、さらには倫理面の課題や誤情報の拡散リスクなど、見逃せない危険性も潜んでいます。
本記事では、最新の調査や専門家の見解をもとに、コトモAIにまつわる5つのリスクを網羅的にまとめました。また、これらのリスクを踏まえたうえで、安全にコトモAIを活用するための具体的な対策も紹介します。
「コトモAIが気になるけれど少し不安」「実際に使っているけどリスクは大丈夫?」と感じる方は、ぜひ最後までご覧ください。

AI導入.comを提供する株式会社FirstShift 代表取締役。トロント大学コンピューターサイエンス学科卒業。株式会社ANIFTYを創業後、世界初のブロックチェーンサービスを開発し、東証プライム上場企業に売却。その後、マッキンゼー・アンド・カンパニーにコンサルタントとして入社。マッキンゼー日本オフィス初の生成AIプロジェクトに従事後、株式会社FirstShiftを創業。
コトモAI(Cotomo)とは?

出典:Cotomo HP
コトモAI(CotomoAI)は、2024年にStarley社からリリースされた音声会話型のAIアプリです。
非常に自然な対話性能と高い共感力を持つことが特徴とされ、キャラクターボイスなどさまざまな音声との会話を楽しむことができます。
本記事ではその危険性を解説しておりますが、コトモAIの概要や使い方について広く知りたい方はこちらの記事をご覧ください↓
コトモAIの主な特徴
コトモAIは特に3つの特徴から注目を集め、ユーザー数が急増しています。
- リアルタイムで自然な応答 ... 音声入力をその場でテキスト化し、自然な返事の出力
- 記憶・パーソナライズ応答 ... 過去の会話を記憶し、ユーザーの状況や好みに最適化された応答
- 匿名利用 ... 2025年3月時点では、メールアドレスや電話番号などの登録なしで利用可能
これらの特徴はコトモAIの利便性を高める一方で、データの取り扱いや依存性などのリスク要因にもつながるため、運営のリスク対策が注目されています。
コトモAIの5つのリスク

ImageFXで作成
コトモAIはその便利さ・親しみやすさゆえにユーザー数を急速に伸ばしている一方で、**「データの取り扱いは大丈夫か?」「依存しすぎてしまわないか?」**といった懸念点・危険性も浮上しています。
以下の表は、コトモAIに関する代表的なリスクを5つの観点でまとめたものです。これらリスクの詳細や対策について、リスク観点別で幅広く解説します。
5つのリスク詳細・専門家の見解
ここからは、先に述べたコトモAIの5つのリスクについて、その詳細を専門家の見解も交えながら具体的に解説していきます。
1. プライバシーリスク

ImageFXで作成
1点目はプライバシーリスクです。コトモAIは個人情報やデータを取り扱うAIサービスのため、それらの情報の扱いについては疑問視がされています。
ここからは具体的に**「会話データの取り扱い」「定型サービスとのデータ連携」「プライバシーポリシー設定」**の3つの観点で、潜在的なリスクを解説していきます。
会話データの保存と取り扱いに関するリスク
コトモAIは音声会話をクラウドサーバーに保存するため、蓄積した音声データの漏洩リスクが存在します。
Starley社は通信経路の暗号化など厳格な保護策を取っていますが、「完全に漏洩リスクをゼロにはできない」ことも公式に認めています。
AIの利用自体にはメールアドレスや電話番号の登録は不要ですが、例えば雑談の中でユーザーが本名や住所、金銭情報を話してしまうと、クラウドに保存されてしまい漏洩のリスクに晒されます。
そのためStarley社は「会話内で個人特定情報は絶対に話さないように」と注意喚起をしています。
提携サービスとのデータ共有に関するリスク
コトモAIは外部のAIサービス(ChatGPT等)と連携しているため、外部AIとの送受信データはStarley社のプライバシーポリシーの適用外になる可能性があります。
また、Starley社が合併・買収など企業再編を行った際には社内データが第三者提供される可能性があることが利用規約に明記されています。その際はユーザーデータが他社に移転されるリスクがあります。
プライバシーポリシー設定に関するリスク
Starley社の公式プライバシーポリシーはユーザーの権利や情報保護を定めていますが**、外部提携サービスまで完全にカバーできていない**点がリスクとして指摘されています。
利用者は常に最新のポリシー更新を確認し、万一の漏洩に備えて「個人情報は話さない」自衛意識を持つことが重要です。
2. セキュリティリスク

ImageFXで作成
2つ目のリスクはセキュリティリスクです。ハッキングやサイバー攻撃にあった際のコトモAIの安全性がいかなるものか、疑問の声が上がっています。
ここからは具体的に**「ハッキングや不正アクセス」「アプリのマイクへのアクセス」「端末の物理的アクセス」「運営のセキュリティ対策」**の4観点よりリスクを解説していきます。
ハッキングや不正アクセスのリスク
コトモAIはクラウド環境で動作するオンラインサービスのため、ハッカーによるサイバー攻撃や不正アクセスにより会話ログの盗聴のリスクがあります。
利用規約でStarley社は不正アクセス等による損害に運営は責任を負わないと明記しており、ユーザー自身による個人情報対策を促しています。
アプリのマイクへのアクセスによるリスク
Starleyではスマホマイクへのアクセス可能に設定にする必要があるため、アプリ利用時以外のマイク音声も取得(バックグラウンド盗聴)されているのではないか、という不安視の声が上がっています。
公式では「バックグラウンド盗聴はしていない」と発表されていますが、不安な場合は使わない時にマイク権限をオフにする、アプリを終了するなどの対策を取ると安心です。
端末の物理的セキュリティによるリスク
アカウント登録が不要ゆえに、スマホを第三者に触れられると会話ログを勝手に閲覧される可能性があります。端末自体に生体認証やパスワードロックをかけるなどの物理的セキュリティも意識しましょう。
運営会社のセキュリティ対策に関するリスク
運営会社のセキュリティ対策が十分か、という点もリスクと捉えることができます。
Starley社はデータ送受信の暗号化や内部規定による厳重管理、ユーザーがデータを削除可能な仕組みなどを整備していると述べており、また自治体との実証実験なども行いながらセキュリティを強化しているとのことです。
一方でゼロデイ攻撃やクラウドプロバイダ側の事故など、企業努力だけで防ぎきれないリスクは存在するため完全防御は難しい、という点は認識しておく必要があります。
3. 倫理的リスク

ImageFXで作成
倫理的な側面からも、コトモAIには一定リスクがあると言えます。
ここでは大きく「出力の偏見・バイアス」「不適切なコンテンツ生成」「感情操作・心理的依存」の3つの観点よりそのリスクについて解説します。
出力に偏見・バイアスが含まれるリスク
ChatGPTやコトモAIのような会話型AIのベースとなる大規模言語モデルは、学習データに含まれるステレオタイプや偏見によって出力するテキストにも差別的な表現が混入する可能性があります。
バイアスの完全排除が技術的に難しい現状も踏まえ、Starley社は「生成物に含まれる社会的偏見等について責任を負わない」と利用規約で明言しています。
運営の責任外となるため、生成物への差別表現の混入はユーザーが自身の目で判断・取り除く必要があります。
不適切なコンテンツが生成されるリスク
AIは入力されたテキストに応じて回答を生成するため、攻撃的・卑猥な内容をわざと投げかければユーザーのプロンプト次第で不適切な発言が誘発される可能性があります。
フィルタリングには技術的な限界があると言われており、コトモAI独自の監視体制は公表されていないため、不適切な応答が出た場合はユーザー通報に頼る面も多いのが現状です。
ユーザーの感情操作・心理的依存のリスク
会話できるAIに対して「親友や恋人のように寄り添ってくれる」と愛着を感じてしまうユーザーが出る可能性があり、専門家は心理的依存を問題視しています。
特に若年層やメンタルが不安定な人ほど影響を受けやすく、長時間使っていると現実の対人関係が疎遠になる恐れがあります。
またAIが励ましたり同意してくれる一方で、有害な考えを無意識に肯定してしまう危険性も指摘されています。
過度に使用しすぎず、AIはあくまでサポートツールと割り切るバランスが重要です。
4. 誤情報拡散のリスク

ImageFXで作成
情報の正確性には、コトモAIについても誤った情報が出力され、その情報が拡散されてしまうリスクが指摘されています。
AIのハルシネーション(誤回答の生成) リスク
大規模言語モデル特有の現象として、**質問に答えるときに存在しない情報を生成(ハルシネーション)**してしまうことがあり、ユーザーには誤情報を受け取ってしまうリスクがあります。
ChatGPTでも「知らない情報をまるで本当のように語る」問題が報告されており、コトモAIにも同様の危険があると言えるでしょう。
コトモAIの回答をそのまま信じるのではなく、他の情報源や専門家に確認するなど、ユーザー自身でのファクトチェックが必要となります。
フェイクニュース・陰謀論の拡散リスク
生成された誤情報はですが、コトモAIの発言を録音・スクショしてSNSに転載すれば、誤情報が外部に拡散される可能性もあります。
- ユーザーが陰謀論的な話をしても、AIが「共感」を重視して否定しないまま流れたりすると、本人の誤解が強まる恐れがあります。
5. その他のリスク

ImageFXで作成
ここまで紹介してきたリスクの他にも、コトモAIを取り巻く危険性はさまざま存在します。
ここでは「法的・コンプライアンス面」と「AI悪用」「企業の透明性」のリスクについて解説します。
法的・コンプライアンス面のリスク
コトモAIの発言が誤って他者を誹謗中傷する内容になった場合、どこに責任が及ぶのかは現行法で明確ではありません。
名誉毀損や著作権侵害について運営会社は免責を主張する可能性が高いため、ユーザーも注意が必要です。
また、将来的に国内外でAI規制法やプライバシー法といったAI関連の法規制が強化されると、コトモAIの運営方針にも影響が及ぶかもしれません。
AIの悪用リスク(詐欺・犯罪利用)
海外ではAI音声を使った音声なりすまし詐欺がすでに報じられているなど、コトモAI自体が悪用された事例は今のところ見当たりませんが、類似技術を用いた振り込め詐欺などのリスクは否定できません。
**自動恋愛詐欺ボット...**AIが人間に成りすまし、大量のユーザーと恋愛チャットを行って金銭をだまし取る手口が海外で確認されています。コトモAI同様の音声・チャット技術が応用される可能性があります。
企業の透明性と今後の動向
**Starley社の姿勢...**プライバシーポリシーや利用規約を公開し、自治体との連携など社会実装にも前向きです。しかし、企業内部に悪意を持つ社員がいればデータ流出を完全に防ぐのは難しいとの指摘も。
**経営方針の変化や買収リスク...**スタートアップ企業であるため、将来的な買収・合併によってプライバシー保護方針が変わる可能性があります。
コトモAIを安全に使うための5つのチェックポイント

ここまで述べたように、コトモAIにはさまざまなリスクが内在しており、ユーザーが適切な使用法を理解することが極めて重要です。
ここでは具体的に守るべきチェックポイントを5つご紹介します。
1. 個人情報を話さない
氏名・住所・金融情報など機密情報を話すことは避けてください。例えばニックネームや仮名を使うなど、自分のプライバシーを守れるような使い方を検討しましょう。
2. AIの回答を鵜呑みにしない
重要な情報や専門的知識は、別のソースで必ず裏取りをし、体調や医療に関する相談などは必ず人間の専門家へ聞くなど、出力された情報を適切に精査するようにしてください。
3. セキュリティ設定・端末ロックを徹底
アプリを公式ストアから入手し、OSやアプリを常に最新に。しておくとともに、スマホ自体の画面ロック、マイク権限のオン・オフ管理を実施し、万全なセキュリティを担保しましょう。
4. 過度な依存を避ける
コトモAIとの会話時間をチェックし、リアルのコミュニケーションも大切に。AIからの承認だけで安心せず、自分の意思や判断を優先するようにしてください
5. 不審な挙動や怪しい誘導があれば通報
規約違反と思われる出力(ヘイト発言、詐欺行為の示唆など)があれば運営に報告をしてください。また、公式アプリ以外のクローンアプリ・不正サイトには絶対にアクセスしない。
まとめ:リスクを理解しながら賢く活用しよう

コトモAIは「人間らしい雑談と共感」をAIで実現する革新的なアプリですが、その裏にはプライバシー、セキュリティ、倫理、誤情報、法的リスクなど様々な懸念が存在します。
運営会社もセキュリティ対策やプライバシー保護に取り組んでいるものの、漏洩リスクを完全になくすことは不可能と公式に言及しており、ユーザーの自己防衛意識が非常に大切です。
**「大きな危険性があるわけではないが、過信は禁物」**というのが専門家の総合的な見解です。基本的な対策(個人情報を話さない、AIを鵜呑みにしないなど)さえ押さえておけば、コトモAIは便利で楽しいコミュニケーションツールとなるでしょう。
今後さらに機能が進化することで、リスクと利便性が同時に高まる可能性があります。アップデート情報やプライバシーポリシー変更に注意を払いつつ、健全な利用を心がけることをおすすめします。
AIサービス導入のご相談は AI導入.com へ(無料)
AI導入.comでは、マッキンゼー・アンド・カンパニーで生成AIプロジェクトに従事した代表を中心に、日本・アメリカの最先端のAIサービスの知見を集めています。AIサービスの導入に関するご相談やお問い合わせを無料で承っております。ビジネスの競争力を高めるために、ぜひ以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。